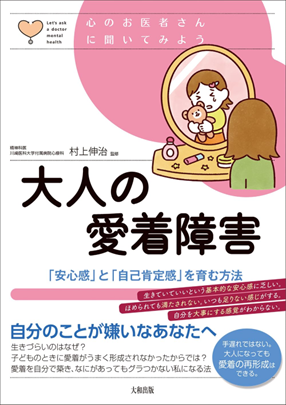「愛着=安心感・自己肯定感」と、タイパ社会の関係性を考える
作成日:2025.4.7
こんにちは、パフの冨田です!
最近、ディズニーシーに行ってきました。
ファンタジースプリングスの新たなアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」に初めて乗りました!

映像も演出も、とにかくアナ雪の世界にどっぷり浸れるアトラクションで、個人的にはファンスプのうち一番好きなアトラクションでした。
まだ混んでいるアトラクションですが、気になる方はぜひ乗ってみてください!
 あなたは自分のことが好きですか?
あなたは自分のことが好きですか?
最近、こんな本を読みました。
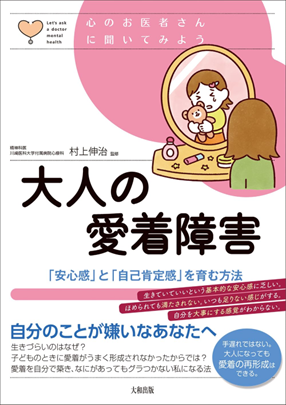
『大人の愛着障害「安心感」と「自己肯定感」を育む方法』
2024年12月15日
著者:村上伸治
発行所:大和出版
突然ですが、質問です。
あなたは・・
・自分をいたわる、かわいがることができていますか?
・いま、自分の味方はいると思いますか?
・自分の中には自分の味方がいますか?
・自分のことがいちばん好きという感覚はありますか?
私は、「いいえ」としか答えられませんでした。。
本書によると、愛着に問題を抱えている人の傾向は、大きく2つあるそうです。
・「自分は生きていていいという基本的な安心感が乏しい(引用:20ページ)」
・「ほめられても満たされず、いつも足りない感じがする(引用:22ページ)」
愛着とは・・
発達心理学における「愛着」とは、乳幼児と母親など養育者とのあいだに形成される特別な情緒的結びつきを意味します。(引用:20ページ)
乳幼児から3歳頃にかけてこうした無条件の愛情を与えられると、子どもは自分を「生きる価値のある存在」「愛されるべき人間」と認識するようになります。この感覚が基本的な自己肯定感の土台となるのです。(引用:21ページ)
また、愛着形成がうまくいかないと、自己がうまく確立できません。自己が不安定で空虚だと、つねに不安なまま周囲に気をつかい続けなければなりません。(引用:23ページ)
日本では、毎年の自殺者は減らない一方ですし、海外の人に比べて日本人は自分に自信のない人が多いと聞きます。
「愛着」に問題を抱えている人は、思ったより多いのかもしれません。
 子どもの成長を急かす子育てを社会が強いている
子どもの成長を急かす子育てを社会が強いている
そのような状況は、社会背景にも問題がありそうです。
共働きの両親と核家族が増えたせいなのでしょうか、家事や育児にも自分の時間や気持ちの余裕がなくなってきています。ますます子どもも「早く大人になってほしい」と成長を急かす親御さんが増えた印象です。(引用:66ページ)
最近、電車やレストランでも、最近スマートフォンやタブレットで小さな子供に動画を見せている光景を見るようになりました。
自分たちは話に夢中になっていたり、別のことをしているのです。
目先のコンテンツで、泣き止ませることができたり、手がかからないように育てることはできるかもしれませんが、「愛着」は育ちにくいのではないのでしょうか。
(子供時代にあまり構ってもらえず、どこかずっと寂しい気持ちを持った状態でここまで育ってしまった私からすると、「もっとゆっくり、真っすぐ向き合ってあげればいいのに」と思います。
・・といっても、子育てしたことない私が言うのもおこがましいのですが。)
「タイパ」は正義か否か
採用シーンでも、「とにかく早く効率的に」という雰囲気が、企業にも学生にも漂っているように感じます。
誰もが時間をかけず効率よくものごとを片付けようとしていますが、こんな時代だからこそ、じっくり相手と向き合い、対話することが重要なのではと改めて感じます。(「ムダ」も「遊び」も、振り返った時には貴重な財産になっている気がするのは私だけでしょうか。。)
本書では、「早く大人になることは、突貫工事で家を建てるようなもの」と例えています。
就活も採用活動も、スピードばかり重視していれば本質をお互い知ることができません。
そうやって入社式を迎えた結果、早期離職に繋がってしまうケースもあるのでしょう。
(ちょうど先日、退職代行モームリさんの投稿で25卒学生が「4月1日に5件、2日に8件、3日に18件」退職代行を依頼されていたという投稿を見て、、見切りをつける速さにも驚きます。。)
・・こじつけがましく採用の話に繋げてしまいました。
それではまたいつか、お会いしましょう。